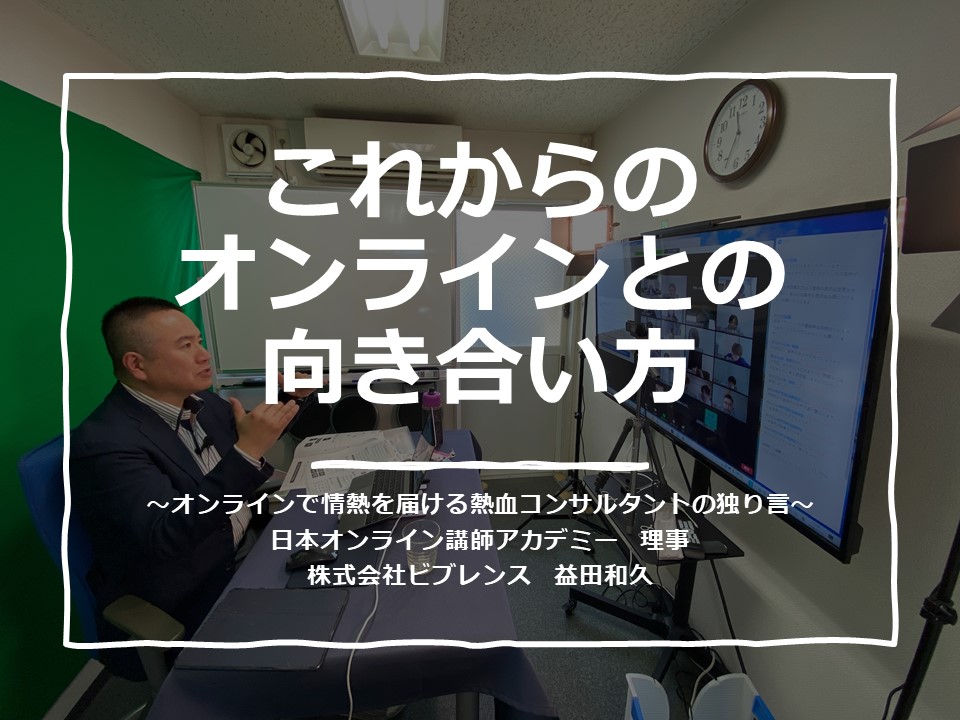先日、日本経済新聞で「採用活動のオンライン化 早期離職の一因にも」という記事を読みました。
お客様からも「考えさせられるよね~」という声をいただき、改めてオンラインコミュニケーションの功罪について考える機会となりました。
記事では、大学の新卒入社で3年以内に早期離職する人が3割強いる現状を取り上げ、コロナ禍以降に広がった採用活動のオンライン化が一因になっているのではないかという専門家の見解が紹介されています。
企業説明会やインターンシップに始まり、就活本番の面接でもオンラインが主流となり、最終面接まで全てオンラインという企業も残っているとのことです。
<オンライン採用の「光」~可能性の広がり>
確かにオンライン就活には大きなメリットがあります。
学生はいろんな企業にチャレンジできるし、その分企業もいろんな学生と知り合える機会が増えました。
地理的な制約を超えて、優秀な人材と出会える可能性は格段に広がっています。
移動時間やコストを考えると、オンラインの効率性は否定できません。
特に地方の学生にとっては、東京や大阪の企業にアクセスしやすくなったのは大きな変化でした。
企業側も、より多くの候補者と接触できるようになり、採用の間口が広がったことは事実です。
<しかし「影」の部分も見逃せない>
一方で、昨今の離職率がオンライン就活と関係があるのではという記事の仮説には、私も賛同します。
企業は実際に訪問してみないと雰囲気はわからないし、働いている人のイメージも掴めません。
どんなにオンラインが進化しても、これは限界があるでしょう。
それは企業が学生を知るという点でも同じです。
画面上から得られる情報は、ある意味表面的なものに留まってしまいます。
実際、最終面接などで学生に会社に来てもらった際、「会ってみるとイメージが違った」という採用部門の話はよく耳にします。
これは学生側にも言えることで、「イマイチ雰囲気が合わなかった」「社員の人を見たときに自分を重ねられなかった」という声もあります。
記事では逆のパターンで、実際に人を見て入社を決めた学生の話が紹介されていましたが、そうした「直感」や「肌感覚」も確かに重要な要素だと思います。
<潜在的なリスクを理解する>
オンラインコミュニケーションを採用活動に使うのは合理的ですが、やはりリスクは覚悟していなければいけません。
オンラインで効率的に人を集めて、結果として早期離職を嘆くのは、誰が悪いわけでもなく、オンラインで交流するという仕組みが持つ潜在的なリスクなのかもしれません。
ただし、オンラインがダメだと言いたいわけではありません。
早期離職の現状を踏まえ、もっといろんな接点を持ち、またシステムやデバイスの進化を活用した接し方を考えるべきです。
<未来への期待と提言>
いきなりは難しいかもしれませんが、五感を刺激できるようなツールもできてくるはずです。
VR技術を使った職場体験、においや触感まで伝える技術、あるいは社員との少人数でのリアルタイム交流会など、まさに目の前で会ったような思いにさせる取り組みを進めてほしいと思います。
これから世界中からいい人材を集めようと思えばなおさらです。
職場見学の360度動画配信、社員の一日に密着したリアルな動画コンテンツ、ARを使った職場環境の疑似体験など、技術的には実現可能なアイデアはたくさんあります。
<バランスの取れた活用を>
結局のところ、オンラインとリアルのベストミックスを見つけることが重要です。
効率性を求めつつも、人と人との深いつながりを大切にする。
そのバランス感覚が、これからの採用活動、ひいてはビジネス全般におけるオンラインコミュニケーションの鍵になりそうです。
私たちの働き方も、オンラインの便利さを享受しながら、リアルな関係性の価値を見直す時期に来ているのかもしれません。