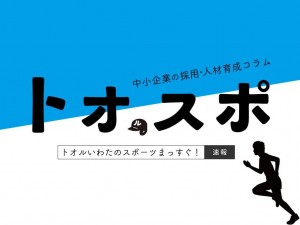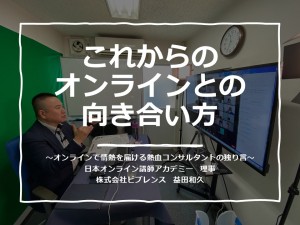10月末、トランプ大統領を囲む夕食会が東京・米大使公邸で開かれ、トヨタの豊田章男会長、ソフトバンクの孫正義会長、ユニクロを手がけるファーストリテイリングの柳井正会長、楽天の三木谷浩史会長ら、日本を代表する企業トップが一堂に会しました。
表向きは“交流の場”ながら、その背後には米国への「巨額投資」を促す意図が色濃くにじみ出ています。
実際、日米首脳会談後に明らかになった「総額60兆円規模」の対米投資計画は、参加企業の今後の経営戦略を占う上で重要なサインといえます。
トヨタは、全米での自動車工場建設や「逆輸入」による新たな販路開拓を示唆し、米国市場への深耕を図っています。
ソフトバンクの孫会長は、再生可能エネルギーやAIインフラ領域での大型投資を視野に入れ、次世代インフラを巡る覇権争いに加わる構えです。
また、ファーストリテイリングの柳井会長は、北米市場でのD2C戦略や店舗網の再拡張を模索しているとされています。
注目すべきは、これらの動きが単なる海外展開ではなく、米国を「戦略拠点」として捉え直す流れにあることです。
高コスト・高リスクを承知で踏み出す背景には、地政学リスクの回避、生産拠点の多極化、そして現地調達・現地販売による供給安定への期待が見てとれます。
国家間の外交イベントを、企業の成長戦略へと昇華できるかどうか。
こうしたトップの動きは、今後、事業ポートフォリオの再設計や人材配置にも波及していくでしょう。
経営層だけでなく、ミドル層にも“世界を読み解く力”が求められる時代が、すでに始まっているのであります。