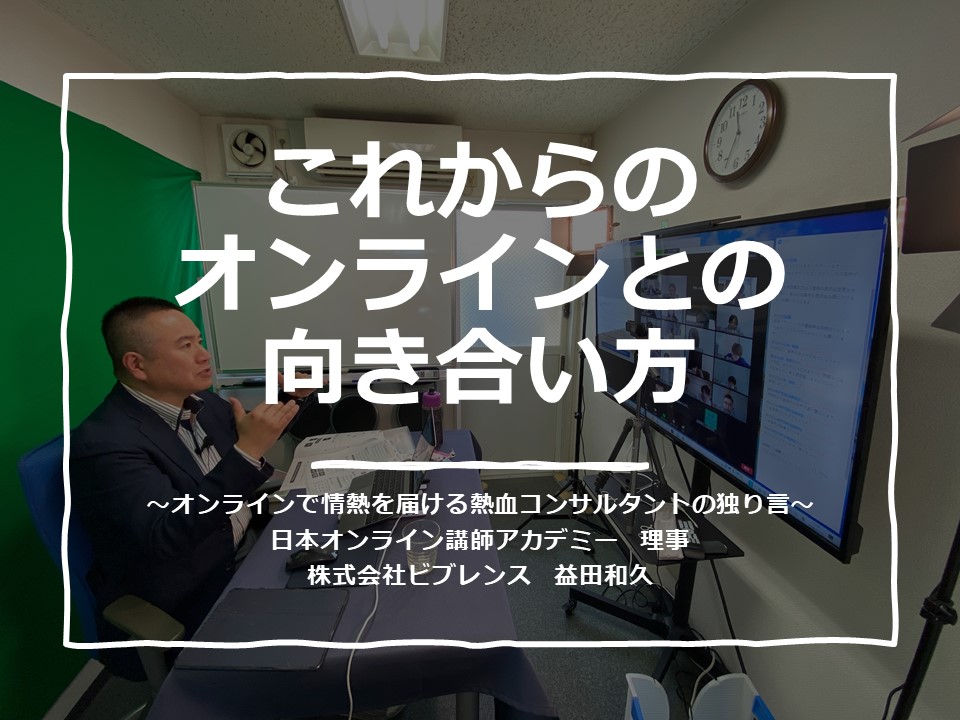先日、日本経済新聞に国勢調査のオンライン活用を促す社説が掲載されました。
我が家でもオンラインで回答を済ませたところですが、この記事を読んで改めて考えさせられたのは、国勢調査が単なる統計調査ではなく、今後の国づくりの根幹の一つだということです。
人事教育コンサルタントとして、デジタル技術と人間の関わり方について日々考えている私にとって、国勢調査のデジタル化は非常に興味深いテーマでした。
記事によると、前回の国勢調査では郵送やオンライン、調査員への手渡しで本人から直接回答が得られたのは8割ほどにとどまり、調査員が周辺から聞き取って補完しているものの、近所づきあいの希薄化などから十分でないとのこと。
そのため政府はオンライン回答比率の目標を5割とし、今回はQRコードで自動ログインできるようにするなどの工夫を施したそうです。
実際、総務省の発表によれば、10月1日午前0時現在のインターネット回答率は約25.8%で、前回調査の同時期と比べ2.1ポイント高くなっているとのこと。
期限である10月8日に向けて、さらなる向上が期待されています。
国勢調査は選挙とは話が違います。
選挙には棄権という選択肢がありますが、国勢調査は統計法により回答が義務づけられており、報告を拒否したり虚偽の報告をしたりした場合は50万円以下の罰金に処される可能性もあります。
つまり、全員が参加すべきものなのです。
その理由は明確です。
国勢調査の結果は、選挙区の区割りや地方交付税の算定基準、社会福祉、雇用、環境整備、災害対策など、あらゆる行政施策の基礎データとして活用されます。
民間企業でも市場分析などに幅広く利用されており、私たちの生活に直結する重要な調査なのです。
町会などのネットワークに入っていれば、リマインドしてくれることもあるでしょう。
しかし記事にもあるとおり、近所づきあいが希薄な最近では、そうしたつながりを持たない世帯も増えています。
納付金などと違って、誰が回答したかがわからないため、罰則があるとはいえ実効性に欠ける面があります。
ましてや案内がポストに入っていても、そのまま忘れてしまうということもあるでしょう。
都市部を中心にオートロックのマンションや単身世帯、外国人世帯が増えており、調査票の配布や回収が難しくなっている現状を考えれば、記事が指摘するとおり、やはりオンライン推進が現実的な解決策になってきます。
オンライン回答の利点は多岐にわたります。
24時間いつでも好きな時間に回答できる柔軟性、繰り返し内容を確認・修正できる安心感、そして調査員との対面を避けられるという心理的ハードルの低さ。
特に若い世代にとっては、スマートフォンから手軽に回答できることは大きな魅力でしょう。
記事では外国人の把握が課題として挙げられていますが、オンライン回答は多言語に対応しているため、言葉の問題を抱える外国人にとっても有効な手段となり得ます。
しかし、ここで一つの大きな課題が浮かび上がります。
それは、高齢者などの情報弱者がデジタル化についていけないという問題です。
これは国勢調査に限った話ではなく、以前から指摘されていることです。
行政のデジタル化が進めば、国勢調査だけでなく、他の行政手続きもよりスムーズになるはずです。
マイナンバーカードの活用、電子申請、オンライン相談など、デジタル技術を活用した行政サービスは今後ますます拡大していくでしょう。
そうした流れの中で、デジタルに不慣れな方々を置き去りにしてはならないのです。
ではこの先、どうすべきなのでしょうか。
私は、やはり高齢者にデジタルに慣れてもらうしかないと考えています。
そのための具体的な取り組みとして、私自身も「東京スマホサポーター」の資格取得に取り組んでいます。
これは東京都が推進する制度で、日頃からスマホを使い、その便利さを知る人が、デジタルに不慣れな方に寄り添い、困りごとの解決に一緒になって取り組むことで、身近な地域での支え合いにつなげる取り組みです。
具体的には、オンライン研修を受講し、すべての講座を修了することでスマホサポーターとして登録され、オープンバッジを取得できます。
登録後は、ボランティアとして各所からスマホ勉強会の依頼を受け、そこに講師として派遣されるのです。
私はまだ実際に依頼は来ていませんが、これが広がっていけば、高齢者や情報弱者の方もデジタル対応が可能になってくるはずです。
私自身は人事教育コンサルタントとして、町会や地域の集まり、同窓会など、いろいろなつながりの中でスマホ勉強会を開いてきました。
しかし、それはあくまで私的なつながりに基づくものでした。
東京スマホサポーター制度のように、これが公的な動きになると、対象者は大きく拡大すると思います。
身近な地域での支え合いという観点からも、非常に意義のある取り組みだと感じています。
デジタル推進は、一部の人だけが恩恵を受けるものであってはなりません。
みんなが協力することで成り立つものです。
デジタルに慣れた人が、不慣れな人を支える。
行政がデジタル化を推進しながら、同時にデジタルデバイドを解消するための仕組みを整える。
そして何より、デジタルに不慣れな方々が「わからないから」と諦めるのではなく、学ぼうとする姿勢を持つ。
この三者がそれぞれの役割を果たすことで、初めて真のデジタル共生社会が実現するのです。
国勢調査のオンライン化は、決してゴールではありません。
それは、誰もがデジタル技術の恩恵を受けられる社会に向けた、重要な通過点に過ぎないのです。
デジタル技術は手段であり、目的ではありません。
しかし、適切に活用すれば、情報格差の解消、地理的制約の克服、そして行政サービスの質的向上という複数の社会課題に同時にアプローチできる可能性を持っています。
政府が目標とする世帯向け基幹統計調査のオンライン化率5割は、決して高いハードルではないはずです。
むしろ、もっと高めてよいと思います。
そのためには、単にシステムを整備するだけでなく、デジタルに不慣れな方々を支える仕組みを同時並行で整えていく必要があります。
東京スマホサポーター制度のような取り組みが全国に広がり、誰もがデジタル技術を使いこなせる社会が実現することを、大いに期待したいと思う今日この頃です。