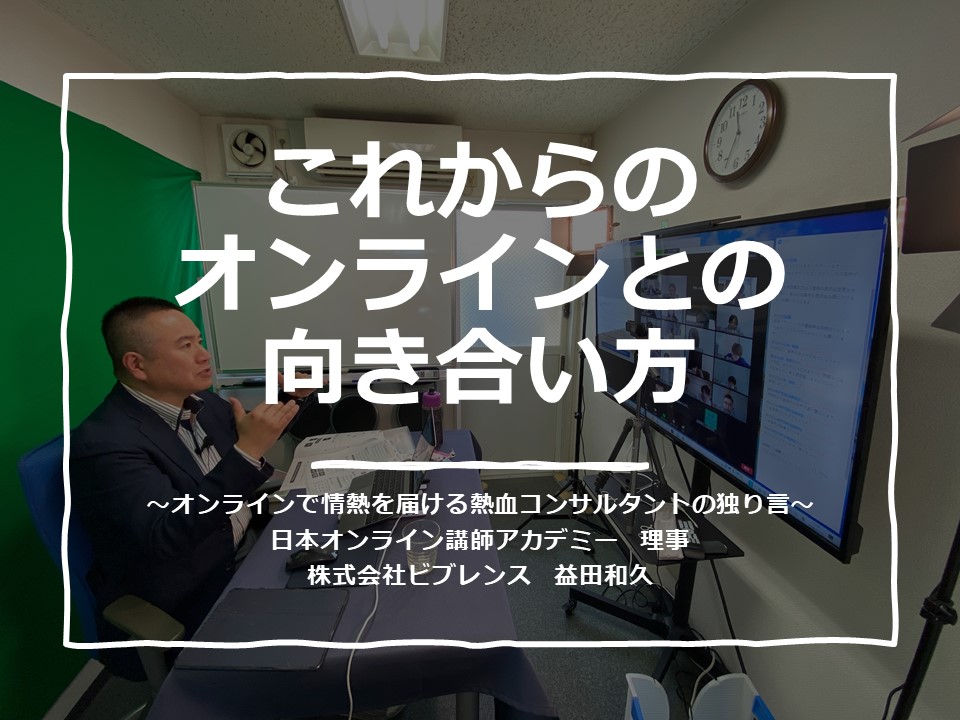この記事がリリースされた前後の日付で「オンライン診療が普及した」という記事が数多く出ていました。
地方圏の10県で実施医療機関が2年で倍増し、青森県では365日全域で小児科オンライン診療を試行開始したとのこと。
オンライン診療をもっと広げていくべきだという自治体やマスコミの意向が働いているように感じられます。
人事教育コンサルタントとして、デジタル技術と人間の関わり方について日々考えている私にとって、この動きは非常に興味深いものでした。
個人的には、オンライン診療推進には大いに賛成です。
特に地方の医療機関不足を、首都圏や大都市圏のリソースを借りることでまかなえるなら、こんなにいいことはありません。
記事にあるとおり、青森県が東京都内の医師らに診察を担当してもらう取り組みは、まさにこの発想の具体化です。
青森県外の医療資源を使うことで県内の医療を手厚くできるという考え方は、地域医療の新しいあり方を示しています。
特に評価したいのは、小児科にスポットをあてて子育てをしやすくしている取り組みです。
青森県の宮下知事が「小児科を受診しやすくして保護者の不安を解消し、子育て環境の充実を図る」と述べているように、オンライン診療は単なる医療サービスではなく、移住を呼び込む子育て支援策としても機能しています。
共働き世帯が増えていく中で通院負担も減るのは大きなメリットでしょう。
毎日午前6時から午後8時まで、平均15分程度の待ち時間で受診できるというのは、働く親にとって本当に助かるはずです。
もちろん、小児科だけではありません。
大人でもちょっとした風邪程度なら、オンラインでも十分対応可能なケースは多いでしょう。
通院時間や待ち時間の軽減にもなります。
とにかく病院は待たされるという不満は誰もが持っているはずです。
記事によれば、オンライン診療で多い病気は風邪が21.5%、新型コロナウイルスが9.0%、適応障害が5.5%とのこと。
こうした症状なら、わざわざ長時間待たされて対面診療を受ける必要性は低いと思います。
処方箋もデリバリーしてもらえる仕組みがあるので、一人暮らしで寝込んでいたりするとホント助かるでしょう。
沖縄県の事例も興味深いものでした。
観光客を呼び込む役割の一手として、看護師を乗せた「ぬちまーす号」がホテルに行き、通信機器で遠隔地から滞在客を診察する取り組みです。
万一の時に医療を提供する安心感は、ホテルや観光地の魅力の一つになります。
オンライン診療は、地域住民だけでなく観光振興にも貢献できるのです。
しかし、問題は対応している医療機関が全国で1割強にとどまっているという現実です。
英国では一般開業医の診療の7割がリモートだったという比較を見ると、日本の普及率の低さは残念に思えます。
なぜ日本でオンライン診療が広がらないのでしょうか。
私が調べた限りでは、いくつかの理由があるようです。
まず診療報酬の問題です。
2022年度の診療報酬改定で対面診療との差は埋まってきたものの、それまでは対面診療との報酬差が大きく、医療機関にとって経済的インセンティブが弱かったのです。
またシステム導入や維持運用のための費用および労力もかかります。
通常の診察の合間や診察終了後に時間を作って行うため、医師だけでなく医療スタッフの負担も増えてしまいます。
加えて、医療機関経営者の平均年齢が約60歳と高齢化しており、IT機器に不慣れな方も多いという実態があります。
新しいITツールを導入することに対して積極的でない場合が多いのです。
オンライン診療への対応が面倒に感じている医師、特に高齢の医師には多いという話も聞きます。
もちろんこれは決めつけではありませんが、私の個人的な取材でも同様の傾向を感じました。
もちろん、医療機関だけの問題ではありません。
オンライン診療を推進するには、医療機関、それを管轄する自治体や国、そしてサポートする協力業者が一体となって取り組む必要があります。
システム開発企業にはより使いやすく、導入しやすいシステムの提供を期待したいですし、国や自治体には財政的・技術的な支援の充実を求めたいところです。
特に小規模な医療機関にとっては、導入コストが大きな障壁となっているため、補助金制度の拡充などが効果的でしょう。
さらに患者側の課題もあります。
高齢者などスマートフォンやパソコンの操作が苦手な方にとっては、オンライン診療のハードルは高いままです。
慢性疾患を持つ患者さんにはご高齢の方が多いため、せっかくオンライン診療は便利だと思っても、参加できない場合が多いのです。
この課題については、前回のコラムでも触れた「東京スマホサポーター」のような取り組みを全国に広げていく必要があるでしょう。
デジタルに慣れた人が、不慣れな人を支える仕組みづくりが不可欠です。
医療機関がもう少し進化すれば、医療は大きく変わると思います。
なぜもっと切り込めないのかと考えると、どうしても政治との関係を邪推してしまいます。
しかし建設的に考えれば、これは医療界全体が抱える構造的な課題であり、一朝一夕に解決できるものではないのでしょう。
それでも、今回の記事で紹介されているような先進的な取り組みが各地で始まっていることは、大きな希望です。
青森県やむつ市、沖縄県など、各自治体が地域の実情に合わせて独自の工夫を凝らしています。
医療DXの推進が叫ばれる中、オンライン診療はその象徴的な取り組みと言えるでしょう。
記事の中で日本大学の田倉智之主任教授が「夫婦共働きの世帯が増え、患者や家族の通院負担は増した。
オンライン診療で軽減することには意義があり、疲弊する地域医療の解決策にもなる」と述べていますが、まさにその通りだと思います。
オンライン診療は単なるデジタル化ではなく、現代社会の変化に医療が適応していくための重要な手段なのです。
もちろん課題もあります。
青森県小児科医会が指摘するように、子どもの体調は急変しやすく、初診でのオンライン診療には慎重であるべきという意見にも一理あります。
だからこそ青森県の宮下知事も、夜間の小児科を補完するのではなく、必要なら対面診療に切り替え、診療後に薬を受け取れる時間帯にしたと説明しています。
こうした丁寧な制度設計が、オンライン診療の信頼性を高めていくのでしょう。
全国で約1万4千の医療機関がオンライン診療を届け出ており、2年間で82.6%増加しています。
これは確かに進歩ですが、まだまだ発展途上です。
沖縄県の2.6倍増、青森県や岩手県の増加など、地方での伸びが目立つのは、医師不足という切実な課題に直面しているからでしょう。
一方で、医療資源が豊かな東京都の伸びを22道府県が上回っているという事実は、オンライン診療が単なる代替手段ではなく、新しい価値を生み出していることを示唆しています。
まだまだ課題の多いオンライン診療ですが、その可能性は計り知れません。
医療機関、自治体、国、システム開発企業、そして私たち患者自身が、それぞれの役割を果たしながら協力していくことで、より良い医療の形が実現できるはずです。
地方の医療格差の解消、子育て支援の充実、観光振興への貢献など、オンライン診療が切り拓く地域医療の未来に、大いに期待したいと思う今日この頃です。