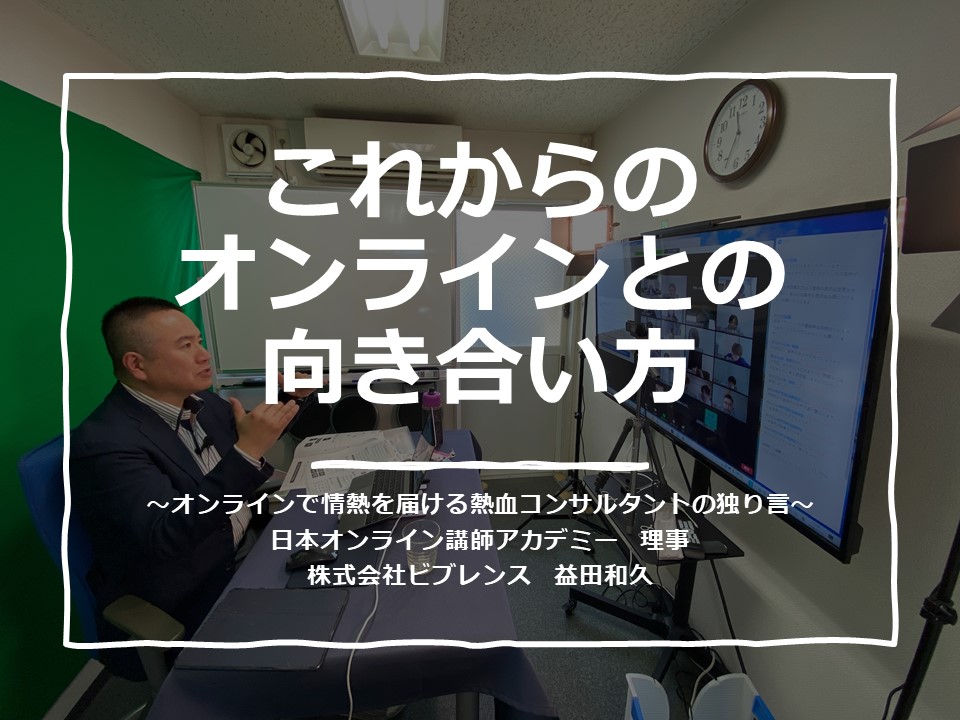先日、興味深いニュースが飛び込んできました。
パナソニックが6月から発売する「レッツノート」の新モデルで、ついにVGA端子を廃止するというのです。
約40年の歴史を持つこの映像出力規格が、事実上その幕を閉じることになります。
記事によると、VGAは1980年代にIBMが初めて採用し普及しましたが、2000年代前半にHDMIが登場すると徐々に存在感を失っていきました。
決定的だったのは「音声出力ができない」という致命的な弱点。
プロジェクターで映像を流しても音声はパソコンのスピーカーから出るため、別途スピーカーを用意する手間がかかっていました。
海外メーカーは早々にVGAを見切り、アップルやインテルなどは2010年代にはHDMIに完全移行。
日本メーカーも富士通は2019年、NECも個人向けでは廃止済みです。
パナソニックだけが「教育機関では一定の需要がある」として採用を続けてきましたが、顧客からの「VGA端子を使わない環境に変わった」という声を受け、ついに廃止を決断したのです。
私が講師として独立したのは2002年。
まさにVGA全盛期でした。
どこの企業に研修で伺っても、会議室にはVGA端子付きのプロジェクターが当たり前のように設置されていました。
青い15ピンのコネクターを差し込む「カチッ」という音は、今でも懐かしく思い出します。
その後、徐々にHDMI対応の機器が増えてきました。画質は格段に向上し、何より音声も一本のケーブルで済むのは革命的でした。
しかし、新しい技術には新しい問題もつきもの。
ある日の研修で、HDMIがうまく認識せず映像が出ないというトラブルに見舞われました。
参加者が待つ中、冷や汗をかきながら試行錯誤していると、会場担当者が「VGAケーブルもありますが...」と救いの手を差し伸べてくれました。
VGAに切り替えると、何事もなかったかのように映像が映し出され、研修を無事に進めることができました。
この経験以来、私は「念のため」という気持ちで、VGAにも対応できるオールインワンタイプの外付けアダプターを持ち歩くようになりました。
HDMI、VGA、USB-C、すべてに対応できる優れものです。
ここ3年ほど使ったことはありませんが、「もしものとき」を考えるとどうしても手放せません。
実際、つい3年前(2022年)にある大手製鉄会社で研修を行った際も、会議室にはVGA端子のプロジェクターがありました。
誰もが知る日本を代表する企業です。
設備の更新サイクルや予算の関係もあるのでしょうが、まだまだVGAが現役で活躍している現場があるのも事実です。
記事の中で、開発担当者が「一部環境ではHDMI端子の普及以降も、VGA端子が利用される設備も残っていた。ご不便をおかけしないよう採用を続けてきた」と説明していますが、まさにこうした現実への配慮だったのでしょう。
しかし、ここで考えさせられるのは、記事の中でディー・エー・シージャパンの鴻池代表が指摘している点です。
「アップルはすぐにVGAを切り捨てて薄型化に舵を切った。日本メーカーは、備えていた方が無難だと発想してしまったのではないか」この指摘は、私自身の行動にも重なります。
VGAアダプターを「もしものため」に持ち歩き続ける私の姿勢も、まさに「備えあれば憂いなし」の典型かもしれません。
リスクを回避しようとする気持ちは理解できますが、それが革新への足かせになってしまう場合もあるのです。
この「備えあれば憂いなし」気質は、日本のDX(デジタルトランスフォーメーション)が進まない根本原因の一つではないでしょうか。
マイナ保険証と従来の紙の保険証の併用、いまだに残るFAXでの業務連絡、古いシステムとの互換性を重視するあまり新しいシステムへの移行が進まない現状。
これらすべてに共通するのは「現在使っている人たちに不便をかけてはいけない」「万が一に備えておこう」という配慮の精神です。
一見、親切で思いやりがあるように見えますが、結果として全体の進歩を阻害してしまっているのが現実です。
セーフティーネットの設け方が根本的に違うような気がします。
欧米では「新しい仕組みに移行する前提で、移行できない人をどうサポートするか」を考えるのに対し、日本では「従来の仕組みを残したまま、新しい仕組みも併用する」という発想になりがちです。
もちろん、マイノリティや弱者への配慮は重要です。
しかし、その配慮の方法を見直す時期に来ているのではないでしょうか。
古い仕組みを温存し続けるのではなく、「どうやったら新しい仕組みに来てもらえるか」を真剣に考える方が、長期的には全体の利益につながります。
デジタルデバイドの問題も同様です。
高齢者がスマートフォンを使えないからといって、アナログの手続きを永続化するのではなく、高齢者でも使いやすいデジタル環境を整備し、サポート体制を充実させる方が建設的です。
今回のパナソニックのVGA廃止は、ある意味で象徴的な出来事かもしれません。
長年続けてきた配慮を思い切って手放し、未来志向に舵を切った決断です。
もちろん、一部のユーザーには不便をかけることになるでしょう。
しかし、それでも前に進む勇気を持つことが、今の日本には必要なのではないでしょうか。
私自身も、そろそろVGAアダプターを持ち歩くのをやめようかと思っています。
3年間使わなかったということは、もうその時代は終わったということです。
万が一VGAしかない環境に遭遇したら、その時は正直に「すみません、HDMI対応のケーブルはありませんか?」と聞けばいいのです。
オンライン化、デジタル化の波は止まりません。
その波に乗るためには、時として古いものを手放す勇気も必要です。
「備えあれば憂いなし」から「未来に向けて針を振り切る」へ。
日本全体がこの発想転換を迫られている時代なのかもしれません。
VGA端子という小さな話から始まりましたが、そこには日本の変革への大きな課題が潜んでいる。
そんなことを考えさせられる今日この頃です。