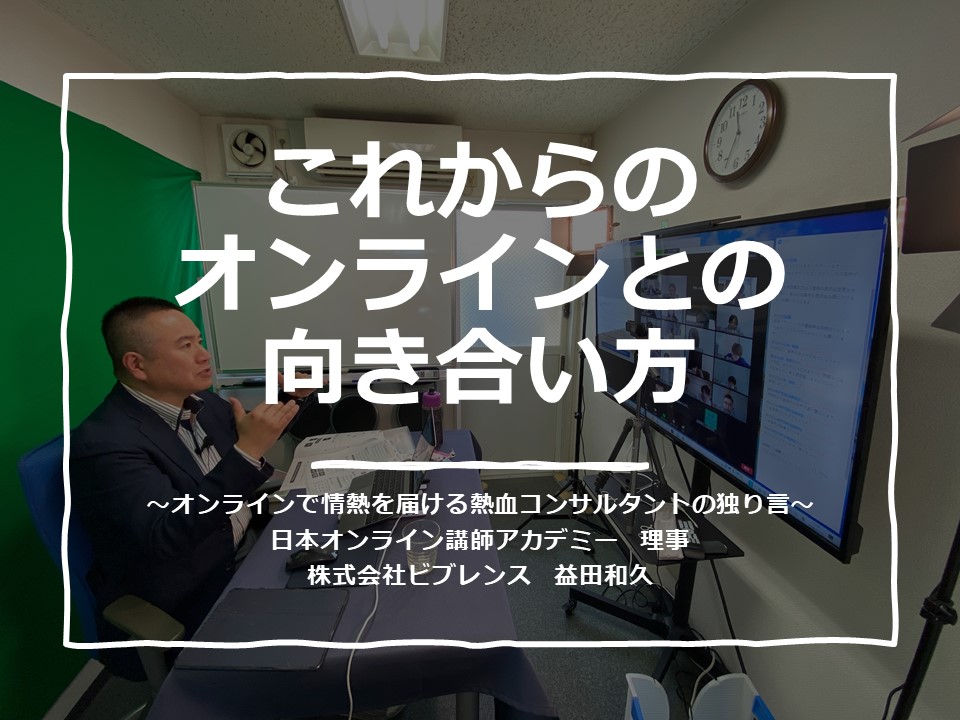先日、日本経済新聞に興味深い記事が掲載されました。
長野県塩尻市が2026年度入庁者の職員採用試験に、対話型AIを使った「harutaka AI面接」を試験導入するというのです。
地方自治体での導入は初めてとのこと。
わずか数行の記事でしたが、そこには自治体が抱える人材確保の課題と、AI技術を活用した新しい採用のあり方が凝縮されていました。
人事教育を生業にしている私の立場からすると、AI面接の導入には基本的に賛成です。
特に自治体での先駆的な取り組みは、大いに評価したいと考えています。
そもそも自治体は前例主義が強く、新しい試みには慎重な傾向があります。
それに加えて、IT人材の不足や予算制約、紙文化の定着など、DX推進において民間企業以上に多くの障壁を抱えているのが現実です。
実際、総務省の調査によれば、人口規模の小さな自治体ほどDXへの取り組みが進んでいないという結果も出ています。
そうした中で、塩尻市が率先してAI面接を導入する姿勢は、他の自治体にとって大きな示唆を与えるものでしょう。
AI面接のメリットは実に多岐にわたります。
まず注目したいのは、応募者が納得いくまで繰り返し面接を受けられるという点です。
従来の面接では、緊張して実力を発揮できなかった、質問の意図がうまく理解できなかったという応募者も少なくありません。
AI面接なら何度でも練習でき、自分の魅力を十分に伝える準備ができます。
また、24時間365日いつでも受けられる柔軟性も大きな利点です。
働きながら転職活動をする人、遠方に住んでいる人には、時間や場所の制約から解放されることは大きな負担軽減になるでしょう。
採用する側にとってもメリットは豊富です。
個別最適化された質問を動的に生成する機能により、応募者一人ひとりの特性や強みを効果的に引き出すことができます。
従来の画一的な質問では見えなかった個性や能力が、AIの質問によって浮き彫りになる可能性があるのです。
さらに、面接官による主観のばらつきを抑え、より公平な評価を実現できることも重要です。
人が行う面接では、どうしても第一印象や雰囲気に左右されがちですが、AIは一貫した基準で応募者を分析します。
加えて、ハラスメント対策としての機能も期待できます。
AIが面接内容を記録・分析することで、不適切な質問や発言を防ぐ環境が整うでしょう。
塩尻市の取り組みで特に評価したいのは、AIが合否を判定しないという点です。
AI面接で収集したデータを、次のフローで行う対人面接で活用し、応募者の特性をより深く理解するための材料とするのです。
つまり、AIは判断を下すのではなく、判断材料をより的確に提供する役割を担います。
この姿勢は、AI活用の本質を正しく理解していると言えるでしょう。
AIに全てを任せるのではなく、AIの強みと人間の強みを組み合わせることで、より質の高い採用が実現できるはずです。
自治体が希望者の減少や多様な人材の確保という課題に直面している現状を考えれば、AI面接の導入は時宜を得た施策です。
公務員の数は減少し続けており、限られた人員で多様化する行政ニーズに対応しなければなりません。
だからこそ、採用段階から最適な人材を見出し、ミスマッチを防ぐことが重要になります。
AI面接は、従来の筆記試験や書類選考だけでは測れない応募者の魅力を可視化し、本当に自治体が必要としている人材を効率的に見つけ出す手段となるでしょう。
塩尻市が学生からの興味や関心を集める狙いもあると述べていますが、これも理にかなっています。
先進的な取り組みを行っている自治体として認知されれば、優秀な若手人材の応募を促すことができます。
もちろん、AI面接にも課題や限界があることは認識しておく必要があります。
どれだけ優れた技術でも、対面でのコミュニケーションでしか伝わらない要素は確実に存在します。
表情の微妙な変化、声のトーン、場の空気を読む力、予期しない質問への対応力といった、人間ならではの判断が必要な場面は多々あります。
また、AIの判断基準が適切かどうかを継続的に検証する仕組みも不可欠です。
AIは学習データに基づいて動作するため、データに偏りがあれば不公平な評価につながる可能性もあります。
技術への過信は禁物であり、常に人間が最終的な判断を下すという原則を忘れてはなりません。
この話から私たちが学べることは何でしょうか。
まず、AIを恐れずに適切に活用する姿勢の重要性です。
新しい技術に対して「よくわからないから導入しない」という消極的な姿勢では、時代の変化に取り残されてしまいます。
DX推進において最も大事なのは、一定のリスクを想定しながらも、ある程度の見込みがあればまず試してみるという行動力です。
完璧を求めて何もしないより、小さく始めて改善を重ねていく方が、はるかに前に進めます。
塩尻市の取り組みは、まさにこの精神を体現しています。
次に、デジタル技術は手段であって目的ではないという認識です。
AI面接を導入すること自体がゴールではなく、より良い人材を採用し、組織力を高めることが本来の目的です。
技術を使うことに満足するのではなく、その技術が本当に目的達成に貢献しているかを常に検証する姿勢が求められます。
みなさんの職場でも、採用や人事評価において「なんとなく続けているけれど、もっと良いやり方があるのでは?」という業務があるはずです。
面接の質問内容は毎年同じで本当に良いのか、評価基準は明確で公平なのか、応募者の潜在能力を十分に引き出せているのか。
こうした問いを投げかけることから、改善は始まります。
AI面接のような新しいツールは、そうした課題解決の有力な選択肢となり得るのです。
大切なのは、現状に満足せず、常に改善の視点を持ち続けること。
そして、新しい技術やツールを恐れずに取り入れる勇気を持つことです。
完璧な解決策を待っていても、いつまでたっても現状は変わりません。
塩尻市のように、まず一歩を踏み出してみる。
その過程で出てくる課題に向き合い、改善を重ねていく。
そうした地道な取り組みの積み重ねが、やがて大きな変革につながっていきます。
AI面接が切り拓く自治体採用の新時代に、大いに期待したいと思う今日この頃です。