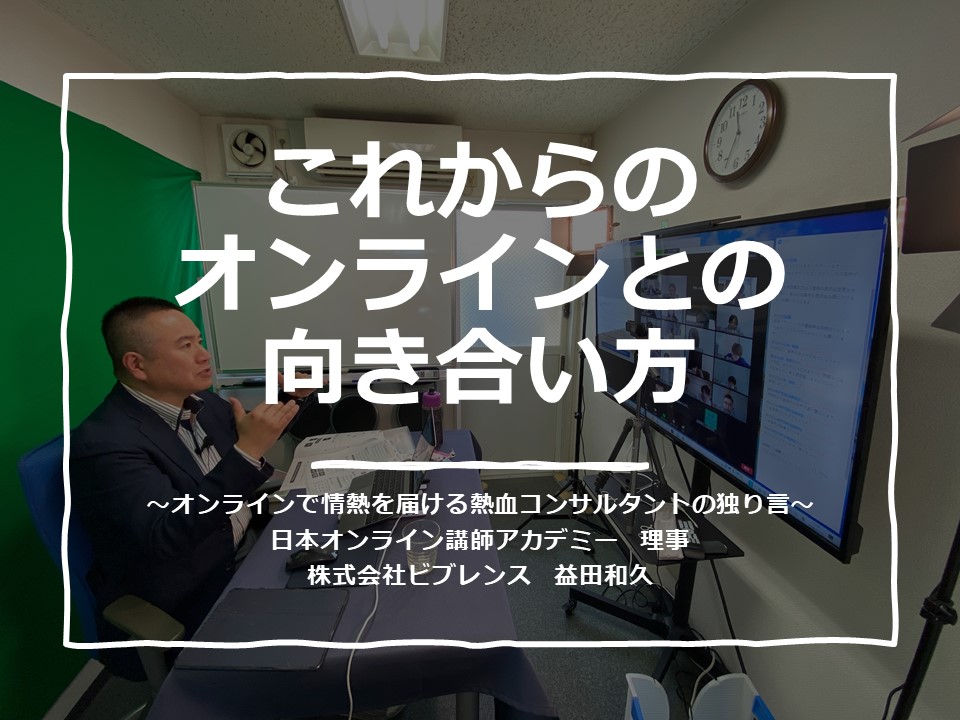先日、日本経済新聞に興味深い記事が掲載されました。
博報堂生活総合研究所が実施した「生活DX定点」調査の結果です。
その中で特に目を引いたのは、「仕事上の謝罪もオンラインでかまわない」と答えた若手社員が3人に1人いるという事実でした。
人事教育コンサルタントとして、デジタル技術と人間の関わり方について日々考えている私にとって、この調査結果は非常に示唆に富むものでした。
調査によると、「オンラインでもかまわないと思うシチュエーション」という質問に対し、「授業参観」「ご祝儀の受け渡し」「退職届の提出」「就職などの面接」では4割以上の人が「オンラインでもかまわない」と回答しています。
さらに10代から20代に限定すると、「授業参観」「就職などの面接」で半数を超え、「ご祝儀の受け渡し」「退職願の提出」も5割に近い数字となっており、若い世代のオンライン化への抵抗のなさが際立っています。
特に注目したいのは「仕事上の謝罪」に関する回答です。
全体では21.7%と少数派でしたが、10代から20代に限ると33.6%と相対的に高い数値を示しました。
多くの人が「どんなにオンライン会議が普及しても謝罪だけは対面だろう」と考えるかもしれません。
しかし、もはや若手社員の3人に1人にとっては、謝罪も必ずしも対面である必要はないのです。
なぜこのような意識の変化が起きているのでしょうか。
小さい頃からスマートフォンを使って育った世代にとって、待ち合わせの遅刻やちょっとした行き違いは、日常的にメッセージで謝罪してきた経験の積み重ねがあります。
彼らにとってオンラインコミュニケーションは、単なる代替手段ではなく、自然なコミュニケーション手段そのものなのです。
調査では生活のデジタル化の実態も明らかになっています。
最もデジタル行動の比率が高かった生活分野は「レシピを見て料理する」で、レシピサイトや動画サイトを見る比率が65.8%に達しました。
「オンライン上で商品を調べる」は60.0%、「自分の創作物をオンライン上で発信する」「店舗での少額決済を電子マネーなどでする」はどちらも50%を超えています。
情報収集、発信、支払いといった分野では、すでにデジタル行動が主流になっているのです。
一方で興味深いのは、生活者の意識です。
「今後、デジタル行動とアナログ行動、どちらの比率を増やしたいですか」という問いに対しては、「特に比率は変えたくない」と答えた割合が最多となりました。
さらに分野ごとに見ても、「アナログ行動を増やしたい」と答えた分野が20分野に及び、「デジタル行動をもっと増やしたい」の8分野を大きく上回っています。
その理由も調査から見えてきます。
デジタル化により「生活が便利になった」「効率が良くなった」という回答はいずれも約7割に上る一方で、「情報に圧倒されることが増えた」と答えた人が全体の約3分の1に達しました。
また、「ストレスが増えた」「疲れやすくなった」と実感する人が、その逆を上回っています。
利便性の向上と引き換えに、情報処理の負担が心身のストレスになっている現実があるのです。
こうした負担は購買行動の変化にも表れています。
選択肢が増えたにもかかわらず、「メジャーな商品を買うようになった」「同じブランドをリピートする傾向が強まった」という人が多く、購買行動が定番化しています。
これは、レビューや口コミへの依存、レコメンド機能による好みの固定化という、デジタル特有の現象と言えるでしょう。
では、こうした状況をどう捉えるべきでしょうか。
私たちは、社会の変化に応じて常識を更新していく必要があります。
固定電話が当たり前だった時代から携帯電話中心の時代へ移行したように、コミュニケーションの形態も変化していきます。
世代によって、業種業界によって、地域によって、適切なデジタルとアナログのバランスは異なるでしょう。
だからこそ、継続的な対話を通じて、その時々の「標準的な考え方」を社会全体で共有していくことが大切です。
ただし忘れてはならないのは、デジタル技術は手段であって目的ではないということです。
謝罪であれば、対面かオンラインかという形式ではなく、誠意を持って向き合い、改善を約束する姿勢こそが本質です。
ご祝儀も、送金方法ではなく、相手の門出を祝福する気持ちが重要なのです。
形式が変わっても、大切にすべき本質は変わりません。
博報堂生活総合研究所の調査が示したのは、デジタル化の光と影が交錯する現代人の姿です。
便利になった一方で、情報過多やストレス、選択の固定化といった新たな課題も生まれています。
これからの社会では、「どんな場面で、どの程度デジタルを活用するか」を、一人ひとりが主体的に選択していく時代になるのでしょう。
そのためには、デジタルに慣れた人が不慣れな人を支え、行政や企業がデジタル化推進とデジタルデバイド解消を同時に進め、すべての人が新しい技術を学ぶ姿勢を持つことが求められます。
デジタル時代の新しい常識を、世代を超えて共に考え、創り上げていくことが大切だと感じる今日この頃です。