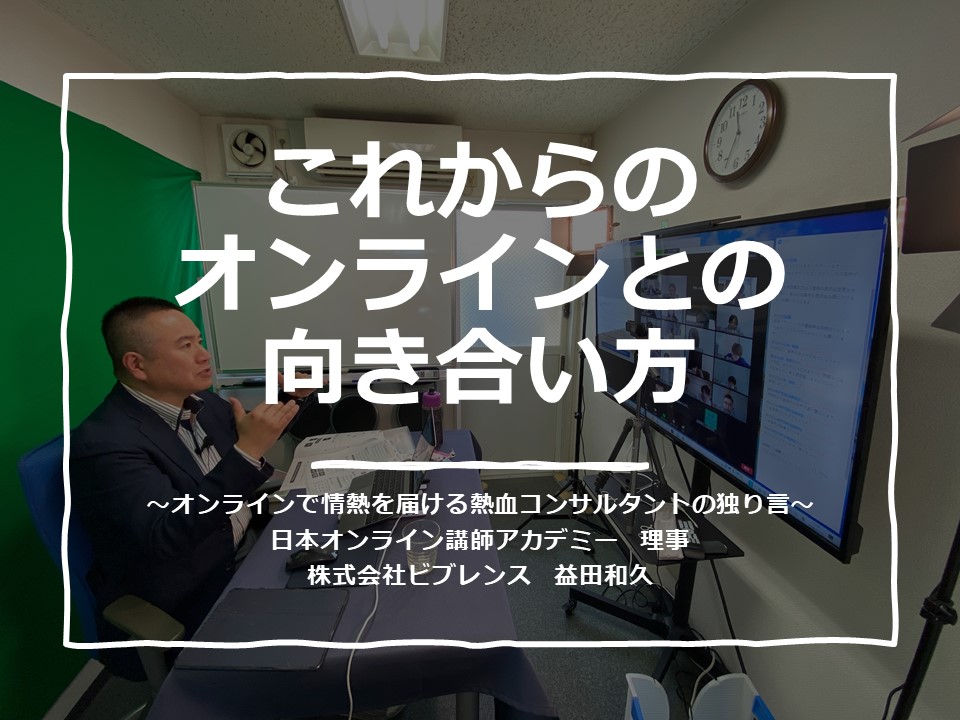日本経済新聞に、ロフトワークと共創施設「SHIBUYA QWS」が5月に開催したカンファレンス「未来デザインとAI」の記事が掲載されていました。
記事によると、約600人のビジネスパーソンが参加し、AI活用における課題と可能性について活発な議論が交わされたとのことです。
製造、建築・技術開発系の大企業から意思決定層と現場実務層がバランスよく参加したこのイベントで語られた内容は、私が研修で日々感じている課題と見事に一致していました。
記事の中で、基調講演に登壇した慶応義塾大学教授の栗原聡氏、パナソニックコネクトの山口有希子氏、そして「#100日チャレンジ」で有名な大塚あみ氏らが指摘した3つのポイントは、まさにDXが進まない企業の根本的な問題を浮き彫りにしています。
第1の壁:「何をしたいのか」が見えない
記事の中で栗原氏は「イノベーションにおけるAI活用は、人の能力に依存する」と指摘し、「AIで何をしたいのか、どうあるべきなのかを考え、理解して判断する能力が、これまで以上に重要になる」と述べています。
まさにその通りです。
DXが進まない企業やチームは、何がしたい、どういう業務改善がしたいというものが見えません。
ビジョンがないわけではないのですが、原因として3つ考えられます。
まず、属人的な仕事の進め方が多いため、業務の可視化や業務分解ができていないことです。
だから何をどうしたいがパッと出てこない。
次に、経営や上司が自分の力量やセンス、経験値だけで考えているから、飛躍的な発想ができないこと。
そして、PDCAは回っているのかもしれませんが、発想の転換ができないことです。
研修でも「どうやって使うのがいいのかよくわからない」「ググるのとどう違うのか」といった声をよく聞きます。
これは単なる操作方法の問題ではなく、そもそも業務の課題が整理されていないことの表れだと思います。
第2の壁:企業文化という見えない障壁
記事の中で山口氏は「DXやAI活用に重要なのは企業文化。
どんなに優れた戦略を立てても、能力の高い人がいても、企業文化が健全でなければ前に進まない」と強調しています。
パナソニックコネクトが先駆けてAIを導入できたのは、風通しの良い企業文化があったからだと記事では紹介されています。
一言でいうと心理的非安全な状況があると思います。
具体的には、風通しが悪いことに気づいていない、新しいものを採り入れる雰囲気がないこと。
上司が旗振りをしない、自分がよくわかっていないから、知らないことだから自信をもって旗振りができないこと。
そして相変わらずの年功序列で、ワカモノが提案することに「何も知らないくせに」といった見下した感覚があるのではないでしょうか。
研修では「会社は操作方法だけざっと説明して(マニュアル配布して)それで終わり、チームでの具体的活用のミーティング時間がとれない」という声もよく聞きます。
一方で「うちが他のチームより進んでいるのは、好きな人がいるから(上司が詳しいから、上司がガンガン使うから)」という話も出てきます。
結局、リーダーの姿勢次第なのです。
第3の壁:「魔法の道具」への過度な期待
記事の中で大塚あみ氏は「ChatGPTは初心者がちょっと使って何か生み出せる、魔法のような道具ではない。専門的な知識を身に付けたプロが膨大な時間を費やしてChatGPTに相談し、言語化できるようになった状態で使って、機能が最大限発揮できるツール」と明言しています。
以前から言っていますが、ChatGPTも部下も同じです。
お願いしたいことの背景や理由、主旨を丁寧に説明して、何度もやりとりをしながらいいものを創り上げていく。
仮に自分が当初思っていたものと違っても、ChatGPTが提示してきたものを受け容れていく姿勢が重要です。ChatGPTを使うからこそ、自分の知見を引き上げてもらう、新しいものを生み出してもらうくらいの感覚が必要だと思います。
記事では、デジタルハリウッドの池谷和浩氏が「人間が道具を使い、道具が人間を変容させていく」と語ったことも紹介されています。
AIを使うことで私たち自身も変わっていかなければなりません。
これら3つの壁は決して乗り越えられないものではないでしょう。
業務の可視化から始まり、心理的安全性を高め、AIとの対話スキルを磨く。
地道な取り組みですが、それこそがDX推進の王道なのではないでしょうか。
約600人が参加したこのカンファレンスが示すように、多くの企業がAI活用の重要性を認識し始めています。
あとは実行するだけなのではないかと感じている今日この頃です。