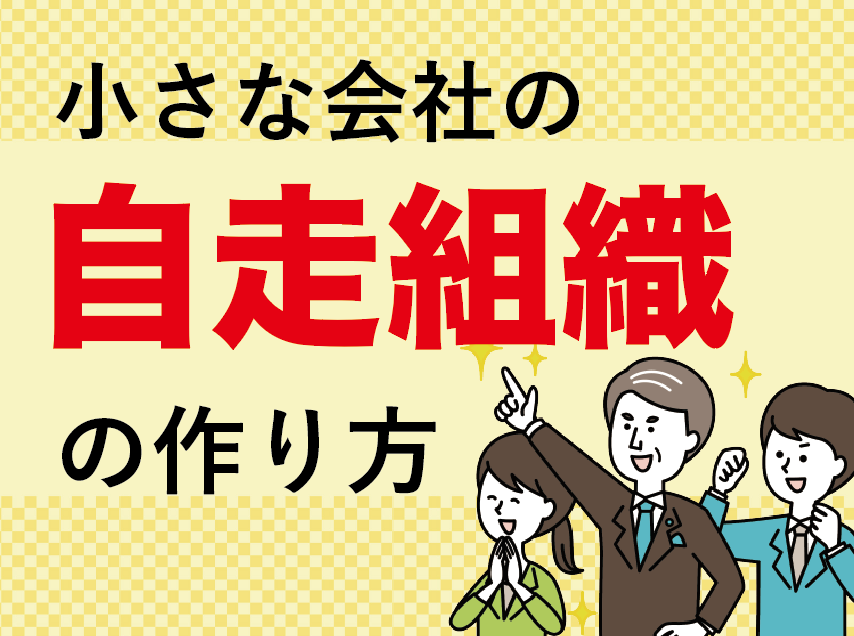「どうして、指示しないと動かないんだろう?」社員たちに対して、そんなふうに感じたことはありませんか?
・自分で考えて動いてほしいのに、何度言っても様子見ばかり
・指示を出さなければ、ずっとそのまま
・やっと行動しても、表面的で浅く、改善の意識が見られない
こうなると、イライラするし、結局「自分でやった方が早い」と、経営者やリーダーだけが疲弊していく。
これ、中小企業では『あるある』です。
でも、ここでちょっと視点を変えてみましょう。
「指示がないと動けない人」は、果たして本当に「指示待ち」なのでしょうか?
私は、社員研修や組織開発の現場で、こういうパターンをたくさん見てきました。
そして気づいたのです。
動かないのは、能力ややる気の問題じゃない。
多くの場合、『信頼残高が足りていないだけ』なのだと。
信頼残高とは?
『信頼残高』とは、簡単に言うと「この人のもとで動いて大丈夫」と思える安心感の蓄積です。
経営者やリーダーからすれば、「そんなの、十分信頼してるよ!」「給料も払ってるし、自由にもしてる!」と思うかもしれません。
でも、それは『信頼しているつもり』であって、社員側からすると、まだ預金が足りていない状態かもしれません。
人が自分で判断し、動くには「失敗しても大丈夫!」という土台が必要です。
ところが、こんな環境だったらどうでしょう?
・自分で考えてやったら怒られた
・前に提案したときにスルーされた
・「なに考えてるの?」と言われて委縮した
・本音を出したら空気が悪くなった
そんな経験があると、人は「様子を見る」「無難に従う」ようになります。
つまり、『考えるより従うほうが安全という学習』が起きているのです。
これは能力の問題ではありません。
「信頼されていない」からではなく、「信頼できない」のです。
環境に、関係性に、そして自分に…。
どうすれば信頼残高を増やせるか?
では、どうすれば社員の『信頼残高』を増やすことができるのでしょうか?
ポイントは3つあります。
① 話を聴くより、「聴かれている実感」を届ける
よく「傾聴が大事」と言われます。
確かにその通りですが、実はもっと大切なことがあります。
それは、『どれだけ聴いたか』ではなく、聴かれていると『相手が感じるかどうか』です。
一生懸命に聴いていても、相手が「聞いてくれてないな…」と感じたら、それまで。
逆に、そこまで深く聴いていなくても、相手が「この人はわかってくれる」と感じたら、信頼残高は一気に貯まります。
つまり、「聴き方の技術」よりも、「伝わり方の工夫」が鍵なのです。例えば、
・「そうなんだね」「そう感じたんだね」と、共感の言葉で返事する
・「それって、こういうことかな?」と、擦り合わせる
・話を途中で遮らず、「うんうん」とうなずきながら聴く
こうしたちょっとした姿勢が、「ちゃんと聴いてもらえた!」という実感を届けます。
意外に思われるかもしれませんが、『実際に聴いたかどうか』より、『聴かれたと思える体験』が、信頼の通帳に記帳されていきます。
② 小さな判断を「委ねてみる」
「これ、任せていいかな?」「自分で考えてやってみてもらえる?」そんなふうに、小さな判断の主導権を、少しずつ社員に渡していくこと。これが、信頼を積み上げる上でとても重要です。
ただし、任せたあとに大切なのは、うまくいっても、いかなくても、「見守る」こと。
そしてもう一歩踏み込んで言えば、そのプロセスを一緒に「味わい、分かち合うこと」です。
たとえば、うまくいったときには…
「◯◯さんのおかげで助かったよ!本当にありがとう。他のことにも応用できそうだから、よかったら、どういう意図でこうしたのか教えてくれる?…なるほど、さすがだね!」
逆に、思うような結果にならなかったときでも…
「最初からうまくいく人なんていないよ。挑戦してくれて本当にありがとう。もしよかったら、今回はどんなふうに考えて動いたのか、教えてくれる?…なるほど、考え方はすごくいいと思う。次はそれを活かしていこう!」
このように、結果だけを見るのではなく、行動の意図や背景に目を向けて承認・感謝する。
たったそれだけで、社員の中にある「自分で考えていいんだ」という感覚が芽生え、「またやってみよう!」というモチベーションに変わっていきます。
小さな任せ、小さな承認の積み重ねが、やがて『自走』という、大きな力に育っていくのです。
③ 結果ではなく「関係性」にフィードバックする
組織の土台は、なんといっても関係性です。どんなに仕組みや制度を整えても、関係性がこじれていれば、うまく機能しません。
逆に言えば、関係性があたたかく、信頼でつながっていれば、「ちょっといいですか?」と、ふと気になったことをすぐに伝え合える。
「こうした方がいいと思ったんだけど、どう思う?」と、遠慮なく話せる。
そんな風土になります。
こうした職場では、報連相も自然に生まれ、お互いに協力しながら「もっと良くしよう」と自発的に動く流れができていきます。
つまり、関係性=自走組織の土台です。
だからこそ、日々の関わり方が何より大事。
「こうした方がよかったね」という『結果への指摘』よりも、
「あなたがやってくれたこと、ちゃんと見てたよ。」
「その行動に、想いを感じたよ。ありがとう。」
「やってみようと思った気持ちが、すごくうれしかった。」
そんな行動の、背景や姿勢へのフィードバックが、信頼残高を着実に増やしていきます。
社員は、「評価」よりも「実感」を求めています。
そしてその実感は、結果ではなく『人と人のつながり』の中に宿るもの。
だからこそ、関係性へのフィードバックが、もっとも深く響くのです。
信頼残高が一定量を超えると、不思議なことが起きます。
・自分から相談に来るようになる
・アイデアを出すようになる
・お客様のことを考えて動くようになる
・「ここ、こう変えた方がいいかも」と言ってくる
これが、自走の始まりです。
そしてこれらは、「指示」や「評価」では引き出せません。
関係性の中にある安心感からしか、生まれないのです。
指示待ちを嘆く前に、問い直してみる
「どうして動かないんだろう?」「自分で考えて動いてほしいのに」そんなときこそ、こう問い直してみてください。
「社員が、安心して動けるだけの信頼残高は、十分あるだろうか?」
「信頼しているか」ではなく、「信頼されているか」でもなく、『信頼しても大丈夫だと思えているか』
この問いこそ、自走組織の第一歩かもしれません。
『社員がなぜか自ら動き出す自走組織』『こじれた関係でも根本から解決できる感情対話』の動画を、【無料】で公開しています。ぜひ、参考にして良い成果をあげてくださいね!
????どちらも【申込不要】ですぐ再生できます!
社員がなぜか自ら動き出す!
▶︎【自走組織の作り方】公開中
こじれた関係が根本から変わる!
▶︎【感情対話の秘密】12分動画