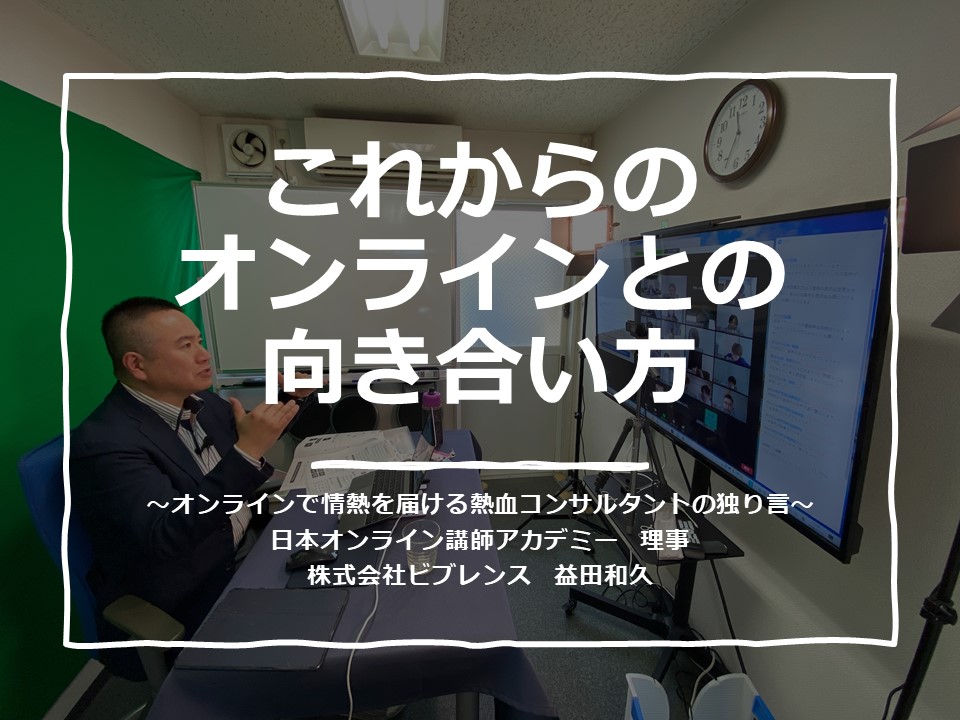日本経済新聞に「さらばアットホーム職場 『任せる上司』求める新入社員」という記事が掲載されていました。
記事によると、リクルートマネジメントソリューションズの調査で、アットホームな職場を望む新入社員の割合が2025年入社では32.5%と過去最低になった一方、上司に「部下に仕事を任せること」を期待する割合は7.5%と2020年の3.4%から倍増したとのことです。
記事では、この変化の背景として、コロナ禍に加えて急速なデジタル化やAI普及による将来不安、SNSで同世代の活躍に触れる機会の増加により「自分も早期に何者かにならなければ」という思いが強まっていることが挙げられています。
新入社員意識調査でも「仕事をするうえで重視すること」のトップは「成長」(35.1%)でした。
記事の分析にある「デジタル化でいろんな人とつながれるから、会社にウエットなものを求めなくなった」という傾向は、年々強くなってきているように感じます。
昔は職場の方とのつながりを大事にしたのは、毎日顔を合わせてつながりやすかったからであり、他に選択肢が少なかったからではないでしょうか。
デジタル化だけでなく、労働時間の短縮や社内のやりとりもメールやチャットが多くなり、顔を合わす(話す)ことも少なくなったから、つながり感も薄いのでしょう。
記事では「オンラインでほかの人たちとのつながりが生まれ、職場以外の多様なコミュニティーに参加しやすくなった」「リモート会議やチャットといったデジタルツールを駆使して業務効率化を進め、仕事以外の時間を生みだすことも可能になった」結果、「職場のウエットな関係性を求めなくなっている」と分析されています。
この流れは今後も加速するでしょう。
社内のつながり方、人間関係の在り方そのものの概念を変えないといけないのかもしれません。
記事では若手社員との向き合い方として、成長機会を体感させる、中身のある指導を受けられると実感させる、期待されていると気づかせる、という3つのポイントが挙げられています。
具体例として、先輩から率直な指摘と営業ノウハウを聞いた、期待を明確に告げられた、他社と比較して自社の良さがわかった方々の事例が紹介されています。
私がOJTリーダー向けの研修をやっているときに、自分がOJTされていた(教えられる側)の立場のときに上司や先輩にされて嬉しかったことというアンケートをとると、上記のことが必ず出てきます。
若手研修の受講者と話すと、それを求めているのを感じます。
これを実践していくためには、「伝える力」が必要です。
会社が本人の能力を伸ばす可能性、会社が本人に期待すること、会社として本人をどう評価しているか、いずれも、伝えるだけでなく、わかってもらうこと、それを聞いて本人に主体的に参画してもらうことも必要です。
管理職は、これらのことが簡単ではないことは認識して、例え反応が悪くても、わかってもらう、動いてもらうまで粘り強く言い続ける胆力が必要でしょう。
また記事では、「心理的安全性」について、単に働きやすいチームをつくることではなく、自発的な学習が広がってイノベーションが起こりやすくなることがポイントだと指摘しています。
職場の「安心・安全」度を高めることばかりに気をとられると、「最低限の仕事しかしない『静かな退職』や早期離職に若手が向かうリスクが出てくる」という警鐘も鳴らされています。
研修で管理職と話していても、心理的安全性が担保されている職場づくりは簡単ではありません。
記事にあるとおり、ゆるい職場になる可能性は十分あります。
実際、「『わからないことは何度も聞ける』のがいいといわれるが、それは本当にその人のためになっているのか」「助け合いが大事なのはわかるが、いつも助けを求められる人は同じでその人に負担がかかる」といった声をよく聞きます。
意味のある心理的安全性のある職場を目指すためには、個人に負担がかからないような仕組みやルールも必要であるし、それなりの従業員教育も必要です。
お互いが成熟した関係でないと成立しません。
管理職向けに心理的安全性をレクチャーすることが多いですが、みんなで目指していくべきではないでしょうか。
いずれにしても、心理的安全性のある職場づくりには、マンパワーに頼らない、マニュアル整備や仕組みづくりが不可欠です。
その推進のベースはやはりDXになるのではないでしょうか。
デジタル時代の職場づくりは、技術と人間性の両面からのアプローチが求められていると感じる今日この頃です。