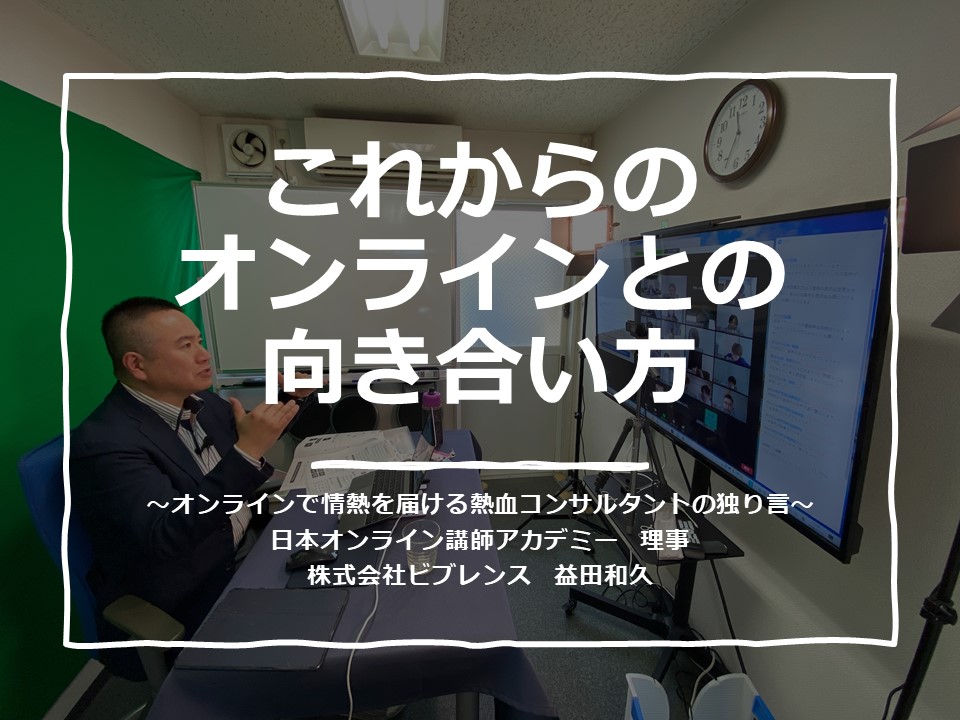日本経済新聞に「広陵の甲子園出場辞退、難しい初期対応 SNS拡散で追い込まれる」という記事が掲載されていました。
記事によると、広陵高校では1月に2年生部員4人による1年生部員1人への暴力行為が発覚し、日本高野連から厳重注意と当該部員の公式戦出場停止の指導を受けていました。
しかし、規則で注意・厳重注意は原則非公表とされているため、当初この情報は公表されませんでした。
その後、被害者側がSNS上で学校の報告以上の苛烈な暴行があったと告発。
学校の報告と被害者側の主張に大きな食い違いがあったことで事態が悪化し、SNSでは憶測も含めた情報が拡散しました。
別の元部員も新たな被害を告発するなど騒動が拡大し、ついに甲子園大会中という前代未聞のタイミングで出場辞退に追い込まれました。
事実がはっきりわからないので、事の発端となっている暴力事件のことや、その後の学校がとった対応の是非について軽々にコメントはできません。
ただ、印象として感じるのは、学校も保護者も高野連も、SNSについて少し甘く見ていたのではないでしょうか。
甘く見ていたというか、ここまで影響があるとは想像しなかったと推察します。
記事では、日本高野連の宝会長が「学校からの報告に基づく審査のやり方自体に改善の余地があるかもしれない。誤情報に留意しながら、時代や社会の変化に合わせて迅速な対応をしなければならない」と語っています。
また、広陵の堀校長も「なぜもっと細かい、お互いが了解しあえるような対応、対処をしなかったのか。それが大きな問題」と後悔を口にしています。
これらのコメントからも、関係者がSNS時代の情報拡散力とその影響の大きさを十分に想定できていなかったことがうかがえます。
結果だけ見れば、ある意味最悪の幕引きだった気がします。
関係した生徒の名前や顔も晒される、それに触発されて罵詈雑言や脅迫行為が発生する、野球部所属の保護者からは全国それぞれの学校に問い合わせが殺到するなど、挙げればきりがありません。
真面目に野球に打ち込んできた生徒や保護者のことを思うと、親としては胸が痛むところがあります。
記事でも指摘されているように、「当事者や周囲を誹謗中傷や差別的言動から守るのはもちろん、第三者による投稿や繊細な個人情報も含んだインターネット上の膨大な情報を正確にどう事実認定するか、指導現場の課題だ」という状況になっています。
2023年の楽天・安楽智大投手のハラスメント問題でも見られたように、アスリートの行動には厳しい目が向けられており、今後もSNSなどで暴力被害が告発されるケースが想定されます。
今回は学校の事例でしたが、企業や団体でも同じことが起こり得ます。
業種や規模にもよりますが、SNS対策は今後力を入れていく必要があるでしょう。
一つの投稿が瞬時に拡散し、組織全体の信頼を失墜させる可能性があることを、すべての組織が認識しなければなりません。
SNSの規制については、あらゆる場面で議論になっていますが、なかなか進まない印象があります。
誹謗中傷に対して開示請求ができるのは知っていますが、どんなオペレーションなのかはわからないのが現状ではないでしょうか。
ましてや、嘘を広められてもそれをストップすることができません。
実際、Facebookに掲載された虚偽広告で堀江貴文さんや前澤友作さんが訴訟していますが、一向に進んでいないようです。
YouTubeなどを見ても、嘘の動画もしょっちゅう目にします。
どうにかならないものかと思います。
ところが、FacebookもYouTubeも、よくわからない理由でバンされることがあります。
私自身は経験ありませんが、友人や知人がバンされた内容を聞く限り、どんなアルゴリズムになっているのかと首をかしげたくなります。
SNS対策に特別なものはないと思います。
発信するときには慎重に。
でも間違いもあったりするからお詫びも迅速丁寧に。
集団になるほど規範や価値観も合わせにくくなるので、日頃から時代の流れに応じた勉強会的なことをする。
そして何より日頃から品行方正に務めることではないでしょうか。
清廉潔白で且つ何かに必死に打ち込んでいる人(団体)に、変なSNSは絡んでこないと思います。
それを証明しているのが大谷翔平選手ではないでしょうか。
記事では「被害者も納得できる解決策をどう探るか、学校側や主催者の初期対応と危機管理のあり方が問われている」と結ばれています。
SNS時代の危機管理は、技術的な対策だけでなく、組織の透明性と誠実性が何より重要だということを、今回の事例は改めて教えてくれているのかもしれません。
デジタル化が進む中で、オンラインとの向き合い方は組織運営の根幹に関わる課題となっています。
予防に勝る治療なしという言葉がありますが、SNS対策においても、日頃の組織運営の在り方こそが最大の防御になるのではないかと感じた真夏の夜でした。