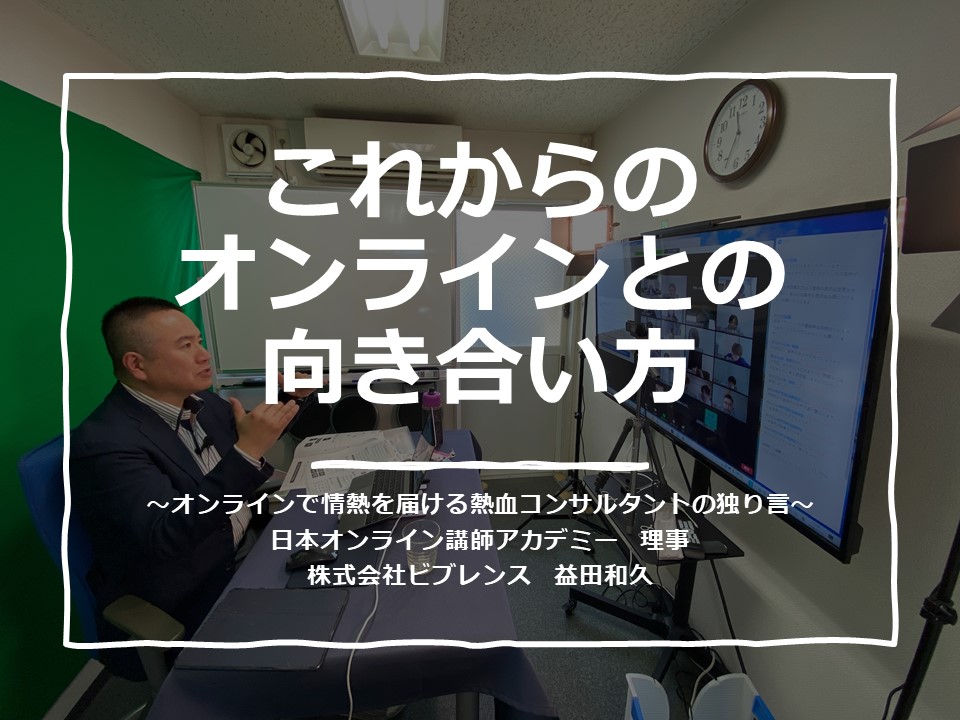先日、ビジネスパートナーとAI活用について話をする機会がありました。
その方は小売業を中心に、ITコンサルやホームページ、デザイン制作なども手がけている経営者です。
AI活用についてはよく勉強もしているし、積極的に業務に活用されています。
実際、GoogleのAI認定も取得しており、私たちパートナーにもAI情報を定期的に発信してくれています。
その会話の中で、改めて感じたことがあります。
AI時代だからこそ、「その人のチカラ」がより重要になってきているということです。
AIの世界は日進月歩どころか、秒単位でニューリリースやアップデートがあります。
ChatGPTの機能追加、GoogleのGeminiの性能向上、新しいAIツールの登場など、毎日のように新しい情報が飛び交っています。
これは単に「遅れをとらないため」という守りの話ではありません。
むしろ、AI技術の進歩を継続的に追いかけることで、従来にない業務手法や、新しい発想、革新的なツールやサービスを創出する機会が無数に生まれているということです。
つまり、零細企業や中小企業が差別化を図り飛び抜けていくには、今は絶好の機会なのです。
これは私見でもありますし、AIを活用している人は同じようなことを言います。
そのビジネスパートナーの方もまさにそうだと言っていました。
以前も書きましたが、AIの出現は、スキル、情報、経験、知見、人脈のない人にとってはチャンスです。
AIの力によって、そのハンディキャップは埋められます。
まさにインターネットが出現し、地域格差をなくしたのと同じような感じです。
実際、地方の小さなデザイン事務所がAIを活用して大手広告代理店と遜色ない提案を作成したり、個人事業主がAIを使って多言語対応のサービスを展開したりする事例が続々と出てきています。
そのビジネスパートナーが語る自社の若手社員のAI活用には、発想、活用範囲、使いこなし方(応用)も含め、感服するものがあるそうです。
以前は自分が指導やアドバイスをしていたが、いよいよ逆転されそうなくらいだと言っていました。
実際、業務も随分と効率化され、新しい提案もどんどん出てきているとのことです。
これは多くの企業で見られる現象です。
デジタルネイティブ世代の若手社員は、AIツールを直感的に使いこなし、従来の業務プロセスを根本から見直すような提案を次々と生み出しています。
ある調査では、20代の8割以上が業務でAIを活用した経験があるという結果も出ています。
このような状況を十分に評価した上で、その会社の社長は若手社員に今後に向けての指導をしたそうです。
その内容が非常に示唆に富んでいました。
デザインを担当するメンバーには: ポスター、美術作品、映画、アニメ、写真集、広告など、視覚表現に関わるあらゆるものに積極的に触れることを推奨。
多様な作品に接することで培われる審美眼や感性がなければ、AIが生成したデザインの良し悪しを適切に判断できないためです。
文書・企画系のメンバーには: 書籍、新聞、各種レポートなど、質の高い文章に数多く触れることを求めました。
豊富な読書体験がなければ、効果的な文章構成や説得力のある企画の組み立て方が身につかないからです。
チーム全体に対しては: 積極的な対人コミュニケーションを奨励。
AIとの対話で適切な結果を得るプロンプト作成は、相手に自分の意図を正確に伝える技術と本質的に同じだからです。
この話を聞いて、ホントその通りだと思いました。
AIが高性能になればなるほど、それを使う人間の「引き出し」の豊富さが問われるようになります。
良いデザインを見極める審美眼、豊富な読書経験に基づく表現力、相手の立場に立って考えるコミュニケーション能力。
これらはすべて、AIを効果的に活用するための基盤となる「その人のチカラ」です。
最近話題になったある事例では、同じAIツールを使っても、美術史に詳しいデザイナーと素人では、出力される作品のクオリティに雲泥の差が生まれたといいます。
AIは道具に過ぎず、それを使いこなすのは人間の知識と感性なのです。
AIが進化するほど、AIをうまく活用してもっといいものをアウトプットできる人と、AIが提示したもの以上のことができない人の二択になってくるのではないでしょうか。
前者は、豊富な知識と経験をベースにAIと対話し、創造的な仕事を生み出し続けます。
後者は、AIの出力をそのまま使うだけで、付加価値を生み出すことができません。
まさにこれからが、真価の問われる時代だと思います。
AI時代だからこそ、読書をし、多様な体験をし、人とのコミュニケーションを大切にする。
そうした基本的な「人間力」こそが、最も重要な差別化要因になるのです。
技術の進歩が速ければ速いほど、それを使いこなす人間の基礎的な能力が問われる。
これが、AI時代の逆説的な真実なのかもしれません。
オンラインツールが発達した今だからこそ、オフラインでの学びと体験の価値を再認識すべきだと感じた今日この頃です。