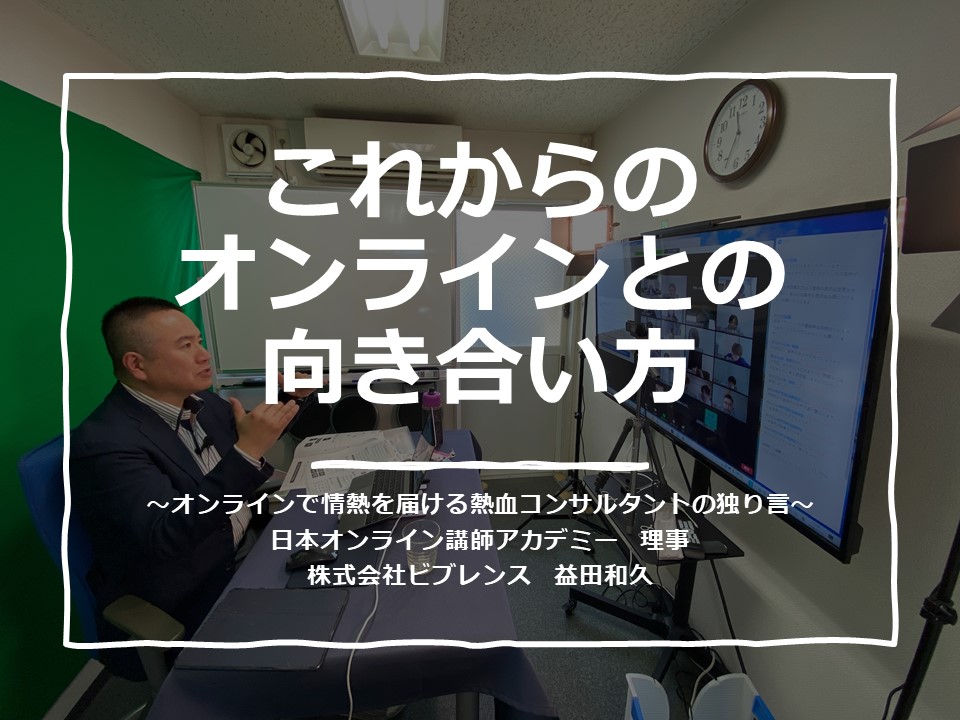日本経済新聞が読者2909人に実施した、生成AI活用に関するアンケート調査の結果が興味深い内容でした。
生成AIを仕事で使う人は65%と、1年前の44%から大きく増加し、このうち7割が業務効率の向上を実感しているとのことです。
ただし、このアンケートに回答した人は日経電子版購読者なので、日頃からオンラインに慣れ親しんでいる方々だと想定されます。
そのため、AI活用という点では平均よりも少し高めの数値が出ているのではないでしょうか。
それを差し引いたとしても、業務でAI活用している人は1年前に比べて随分と増えたというのが実感です。
私が登壇する研修の参加者に聞いても、この変化は体感ベースでよくわかります。
PwCの調査でも、生成AIを「業界構造を根本から変革するチャンス」と捉える企業の55%が期待を大きく上回る効果を創出しているなど、組織的な取り組みの重要性を示すデータが次々と発表されています。
また、情報の正確性や情報流出に対する懸念が下がってきているのは、RAG(検索拡張生成)を利用した自社専用AIや自社サーバー内だけでの利用といった、自社データを安全に活用できる仕組みが定着してきているからでしょう。
矢野経済研究所の調査でも、2024年は25.8%の企業が生成AIを活用しており、前年の9.9%から大幅に増加していることが確認されています。
しかし、利用環境の整備については、かなりのバラツキがあるのが現実です。
日経の調査によると、AIの利用ルールがある人は49%とほぼ半数止まり。
自社用のAIツールが導入されている人はわずか24%でした。
業種別の格差も顕著です。
自動車では40%、電気・電子機器では39%、金融では30%が自社ツールがあると答えた一方、食品・医薬などは17%、卸売業・小売業などは10%という結果でした。
この格差の背景には、いくつかの要因が考えられます。
製造業や金融業のような業界では、従来からデジタル技術への投資や情報システムの整備が進んでおり、生成AI導入の土台ができています。
一方、食品・医薬や卸売・小売業界では、業務の性質上、まだ人間の判断や対面でのコミュニケーションを重視する傾向が強く、AI導入への積極性が相対的に低いのかもしれません。
また、情報通信総合研究所の調査では、従業員数1,000人以上の企業とそれ以外で導入率に倍以上の差があることも報告されており、企業規模による格差も無視できません。
私が企業訪問をする中でも、導入がうまくいっているところは、間違いなく管理職が活用への旗振りをしています。
具体的には、チームミーティングで議題にする、改善活動で提案する、自分が率先利用するといった取り組みです。
PwCの調査でも、期待を大きく上回る効果を得た企業の約6割が「社長直轄で推進している」と回答しており、トップの関与が成功の分かれ道となっています。
会社の本気度や従業員の利用欲求にも左右されているのかもしれませんが、使う度合いは職種や立場によって違うにせよ、社内全体として積極的に活用していこうという機運が何より大事ではないでしょうか。
米国企業では生成AIを新しい顧客体験創出や新規事業投資に活用し、イノベーションサイクルを回しているのに対し、日本企業は既存業務の効率化に留まっている傾向があるという指摘もあります。
個人任せでの活用では限界があります。組織全体でルールを整備し、ツールを導入し、管理職が率先して活用する。
そうした環境づくりができているかどうかで、今後の競争力に大きな差が生まれることでしょう。
AI活用は、もはや「やってみよう」の段階ではなく、「みんなでやっていこう」の段階に入っています。
組織ぐるみで取り組みを始める時期がきていますが、みなさんの所属する組織はいかがでしょうか?