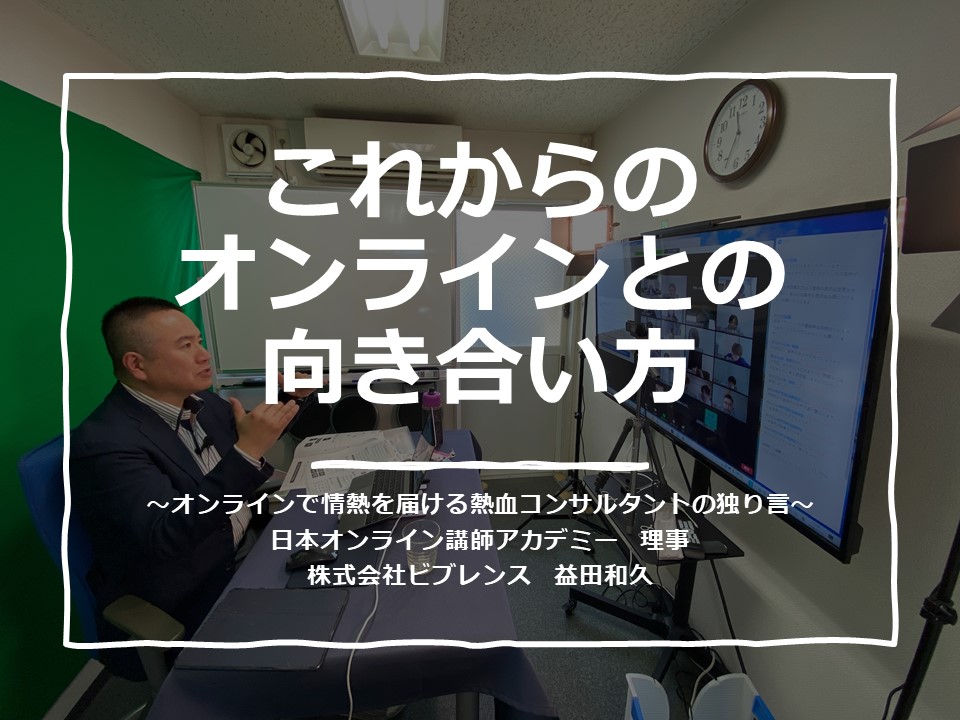兵庫県が全国初となる「いじめ防止条例改正案」を県議会に提出しました。
SNS利用制限を保護者の努力義務とする内容です。
文部科学省の調査によれば、2024年度の小中高でのネットいじめは約2万7千件で、5年前と比べて1.5倍に増加しています。
特に小中学生での伸び率が大きいということです。
この問題を論じる前に、私の持論を明確にしておきたいと思います。
いじめは、いじめる側が100%悪い。
そして現在、多くのケースは単なるいじめではなく、既に犯罪の領域に入っています。
この認識を、私たち大人はもっと強く警告していかなければならないと考えています。
日経新聞の記事で、いじめ相談アプリ「スタンドバイ」を運営する谷山大三郎さんが指摘していたのは、ネットいじめの「巧妙化」です。
例えば、仲良しグループの中で特定の子を疎ましく思った子が、チャットアプリのプロフィール欄を「ムカつく」と変更する。
誰を指しているかは明示しないが、対象となった子は自分のことだと察して傷つく。
抗議すれば「自意識過剰」と言われ、何も言わなくても傷つく。
心理学でいう「ダブルバインド」の状態です。
今の子どもたちは、明確な証拠を残すようないじめはしません。
加害者として特定されれば、自分がさらされて被害者になる可能性があることを知っているからです。
だが、人を傷つけたい気持ちはあって、それを見えにくい形で実行している。
デジタルネイティブ世代の子どもたちは、無意識のうちに巧妙さを身につけてしまっているのです。
こうした状況に対して、社会が一定のガイドラインを示すことは必要だと考えています。
以前、愛知県豊明市がスマホの利用を1日2時間以内とする条例を施行したことを、このコラムでも取り上げました。当時も賛否両論がありましたが、仏教大学の原清治教授が今回の記事で指摘しているように、「子どもの世界に大人が介入し、基準を示し始めた。これは大事」なのです。
完璧なルールを作ることは不可能かもしれません。
しかし、社会が「これは問題だ」という姿勢を示すことで、家庭や地域での会話が生まれます。
「なぜ長時間スマホを使ったらダメなのか」という対話のきっかけになる。
それこそが重要なのではないでしょうか。
今、子どもたちには話し相手がいなくても、友達がいなくても、スマホがあります。
いろんな人ともつながれるし、情報も収集できる。だから表面的には寂しくないのかもしれません。
しかし、見なくてもいいものも見てしまう。
エコーチェンバー効果によって偏った考えが形成されてしまったり、善悪の判断がつかなくなってしまったりする危険性があります。
そして何より、家庭での会話が少なくなっていることは事実です。
スマホの画面を見つめる時間が増えれば増えるほど、顔を見合わせて話す時間は減っていく。
この状況を是正するためには、まず社会が一定のガイドラインを示し、それに基づいて各家庭や地域でルールづくりを進めていくしかないと思います。
原教授も指摘するように、学校で一律にネット利用のルールを決めても、家庭によって生活リズムは異なります。
だからこそ、「家庭のローカルルール」を作ることが大切なのです。
その過程で家族がいろんなことを話し合う。
それによって、リアルでもネットでも、良い生活へと向かっていけるのです。
これは何も子どものいる家庭だけの問題ではありません。
職場でも同じことが言えるのではないでしょうか。
若手社員のスマホ利用について、皆さんの組織ではどんなルールや共通認識があるでしょうか。
休憩時間や移動時間にスマホを見ることは当たり前になっていますが、それが職場でのコミュニケーションにどんな影響を与えているか、立ち止まって考えてみる価値はあります。
健全なデジタル社会を創り上げるためには、規制だけでなく、対話が必要です。
家庭で、地域で、そして職場で。画面の向こうではなく、目の前にいる人と言葉を交わすこと。
その積み重ねが、ネットいじめのような問題への、本質的な処方箋になるのではないかと思う今日この頃です。